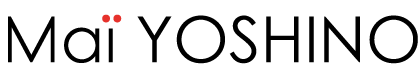『繕い裁つ人』は、服を作り、売ることについての物語だ。
主人公は、祖母が創業した町の仕立て屋を継いだ若い女性。町の人たちの「こういう服が着たい」という希望を聞いて、デザインを提案し、「世界でたった一点」の服を自分で仕立てる。オーダーメイド(注文服)の世界だ。
ファストファッション全盛で1シーズンしか着られない服が簡単に手に入る時代、こういう主人公が出てくると「マス批判」「手作り礼賛」のような感じになりそうだ。だが、そうならない。そこが面白い。
仕立てる
オーダーメイドでつくられる服は一点ものだ。混同されることがあるが、同じく「たった一着」をつくるオートクチュールとは、全然違うものだ。
「オーダーメイド」は、「こういう服が欲しい」という顧客に対して、仕立て屋が服を仕立てる。つまり、デザインの原点に、顧客の都合がある。
「オートクチュール」は、デザイナーが「次のシーズンはこのデザインで」と考えたデザインを元に、アトリエでサンプルをつくり、それをモデルに着せて発表する(「ショー」とか「コレクション(の発表)」というのがこれ)。顧客はそのサンプルをみて「このデザインが気に入った」と選び、そのデザインで、こんどは自分の体型に合わせて服を作ってもらう、そういうシステムだ。現在でもファッション界の頂点にある。
つまりデザインに、顧客の事情は反映されない。選ばれたデザインを顧客の希望でアレンジするということも、ない。結果、どうなるか。モデルの体型では素敵だったけれど、普通の人の体型ではそれほどには(一着何百万、何千万と払うほどには)素敵でないということも、ありうる。
オートクチュールは非常に高価で、限られた人のためのものだ。だから全体としては、ほとんどの人が(オートクチュールの服の載った雑誌の切り抜きなどを持って「こんな感じ」と仕立て屋に行って)「オーダーメイド」で作られた服を着る時代がずっと、続いていた。それが次第に、とくに20世紀後半から既製服全盛時代になり、すでにデザインが決まって、標準的な体型のためにつくられた服を(多くの場合S,M,Lと「大きさ」は選べるが、特に腰が広いとか、首が長いなど特徴のある体型は切り捨てられる「シビアな世界よね 数字で分けられるんだから」)、選び、着るようになる。それがけっして自分のために作られた服ではないと知りつつ。
オートクチュールのシステムが確立したのは、1857年。イギリス人のシャルル・フレデリック・ウォルトによる。これによって、デザイナーは「服」ではなく「デザイン」を売ることになり、「出入りの職人」から「芸術家」へと徐々に地位を上昇させる。イヴ=サンローランなど、誰もが知っているスターデザイナーも出た。逆にいえば、デザインを押し付けない人間―職人の地位は、その間それほどには上昇していない。
「繕い裁つ人」
さて『繕い裁つ人』の主人公―市江は、その「職人」の側で「服を作り、売る」人間だ。顧客となる人がもっとも生かされる服を仕立て、それを通してその人の身体と人生に寄り添う。たしかにそれは「人の人生に触れられる希有な仕事」だ。だが報われることは多くない。(「でもみな服には目もくれないわね」)
顧客と仕立て屋の強い想いで作られた服は、時にさらに強い、ネガティブな想いをも背負う。どんな創作物も創作者の分身だが、そこにさらに着る人の人生まで重ねられれば、ネガティブにもすごい破壊力を持つことになる。危ない。(「ああ あのドレス すごい勢いで切り刻んでたわ 服といっしょに憎しみも引き受けたんだとか言って」)
おまけに職人であることは、貧乏(すれすれ)であることだ。
『繕い裁つ人』の主人公は、けっして豊かではない祖母の生活をずっとみて育った。どれほど素晴らしい仕事をしても、売れっ子になっても、やっぱり貧乏「すれすれ」だ。引き受けられる仕事の量が決まっている。そして身体が資本だからだ。心で物をカバーできるときばかりではない。(「なあ市江 お前がどんなときでも美しいものに感動できるなら それほど豊かなことはないと私は思うよ」「おばあちゃん それは心の話 市江は物の話をしてるんだよ」)
たしかに想いの重さが、すばらしいかたちで結晶することはある。(「俺らが学生の頃 見て絶句したドレスだ これを見てると ドレスに斬新さやデザイン性が必要かって思うよ」「ちりばめられてる石はぜんぜん高価なものじゃない 模造ガラスなんだけどね 糊付けなんてされてなくて 全身にほどこされた刺繍に見事にはめこまれてるの」)
だが「一点もので」「(比較的)高価な」服を注文し、つくることは、注文する側にとっても、創る側にとっても、「高価な重荷」だ。
どう転んでも「重い」。
この重苦しい割に合わない人生を、主人公はなぜ、選ぶのか?
それが「自分のやること」だからだ。
自分が「繕い裁つ人」だからだ。
「定番」
「自分のやること」にまっすぐに進むのは、主人公だけではない。この作品では、それぞれの人間が、それぞれの選択のなかで「服を作り、売る」。
主人公も認めるすぐれたデザインの才能を持つスターの卵も(「俺ねー夢なんすよね 俺の作った服着た女の子たちが通りにあふれるってのが」「縫製なんて自分でやる気ねえし [...]こんなちっちゃな仕立て屋 目指してるわけじゃねえし」)、すでに有名なデザイナーも(「オーダーメードはやんないよ 人間のほうが服に合わせりゃいいって思ってるからね だってほら 服のが理想的なパターンで作ってんだから」)、主人公と同じけれどさらに年配の仕立て屋も(「たった一人の方に最高の満足をしていただくのと 多くの方からそれなりの評価をいただくのとは全く違いますからなあ」)、同じように「自分のやること」を選び、進む。
だからこの作品に出てくる「服」のプロフェッショナルたちは、同じ道を歩まなくても、認め合い、尊敬し合うことができる。残念なお客さんは多少いるが、ブレたプロはいない。そういう人たちが互いに、認め、認められている。だからこの作品を読むのはほんとうに、気持ちがいい。
この魅力的な登場人物たちは間違いなく、作者の分身だ。作者自身、「自分のやること」「できること」が何かをつきつめながら、描いているから(「できないことはやらないだけです。コマ割りも、斜めのカットさえ最初はできなかったんです」)。
登場人物が互いに「やること」「できること」を尊重できる、これも作者の意思だ。(「何かを批判したり一方に偏りすぎないで、いろんな側面を描きたい。」)
こんな風にして書かれた作品は、何になるか?
「服」についての「定番」マンガ。それが、生まれつつある。
だから「服」について考えたい人にはかならず、この作品を薦めたい。
そしてものを「作り、売る」全ての、人に。
俺は名前だけ残ったって嬉しくないっす 何百年先まで俺の作った服を着ててほしんすよ それにはやっぱり定番を極めるのがいいかと思って
たまに考えるもんね 自分が死んでも残る服を作ってるかって
----------------------------------------
掲載『マンガHONZ』