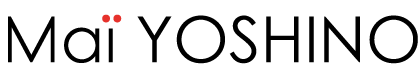高橋真琴は、少女マンガの瞳に星を描いた最初のマンガ家だといわれる。(本人曰く、「よく、そう聞かれるのですが、いつからとはっきり言える記憶はないのです」。)コマをぶち抜いて統合するファッショナブルな人物を描いたことでも知られる。出てくる要素は、パリ、バレエ、ドレス、金髪や茶色の巻き髪、女子同士の友情、お姫様。キラキラきらめく少女マンガっぽさ、を作った一人だ。
『パリ~東京』は、そんな高橋真琴の、瞳に星が入り、素敵なドレスに身を包む人物がコマをぶち抜くようになる直前、貸本漫画時代の、作品だ。
この直後、高橋真琴は光文社の雑誌『少女』で雑誌デビュー。絶大な人気で、多忙を極め、当時出版社が飛行機代を出して呼び寄せたのは、手塚治虫と高橋真琴だけだったという。
『パリ~東京』とフランス語

さて、『パリ~東京』、とても変わったマンガだ。
1頁目をめくる。「女の子というものは生まれつき美しいものへ憧れる心を持っています そして花や星をほしがるものです」。吹き出しを使っておらず、挿し絵のついた小説のような感じだ。
6~7頁。見開きいっぱいにパリの地図(セーヌ川と名所のみ)。その上に、タイトル『パリ~東京』と、作・画 高橋真琴という情報が、フランス語と日本語の両方であしらわれる。そして頁の脇に、「頁の横に会話や単語をフランス語で入れてみました。お友達どうしで使ってごらんなさい きっと会話が今までよりいっそう楽しいものになるでしょう(強調筆者)」と、ある。
フランス語は頁脇に出てくるだけではない。もう少し先に進むと、登場人物たちはとつぜん、平然と、フランス語と日本語のちゃんぽんで話し出す。
いったいどんなわけで、こんなマンガが生まれたのか。
作家自身の語るところによれば、こういうことらしい。
フランス語は当時、ラジオでフランス語講座を聞き始めた頃で、誰もそんなことを試したことがないから面白いかなと思ったんです。
『パリ~東京』読本
作家が、ラジオ講座でフランス語の勉強をしているから、読者に意味が通じなくても、登場人物がフランス語で話しだす、今のマンガではぜったいに起こりえない。ちなみにフランス語のやりとりが出てくるところは、まさにラジオで作家が学んだばかりであるであろう、「出会いとあいさつ」「レストランでの注文」などの場面だ。
ストーリーは、あえていえば、「ヒロインの母は少女小説の売れっ子挿絵画家で、父がいない、その父(やはり画家)がじつは、パリで...」というもので、かなりとってつけたようなストーリーだ。
基本的には私は、マンガは絵がいくら素晴らしくても、ストーリーが面白くなければ意味がない、と思う。その日頃の基準で言えば、これは「絵は綺麗なんだけど...」と残念なグループに入るマンガだ。けれども『パリ~東京』は、頁をめくりたくなる。頁をめくれば、かならず幸福感を感じる。他にはない、不思議な魅力がこの本にはある。それは何か?
「一頁の価値をできうる限り高める」という作家の挑戦だ。
一頁の価値を高める
その心意気は、作家の次のことばからも伝わってくる。
森を描くなら、その森に小動物がいて花が咲いていて、木の葉の描き方で季節感もちがって、という風に森そのものに生命感をもたせたいと思うんですね。主人公がお部屋にいるならインテリアにも工夫したい。テーブルの上にはお茶やお菓子もあると素敵だろうと[...]
『パリ~東京』読本
サービス精神とも、職人魂とも言ってよいこの挑戦は、ときに、とつぜん登場人物がフランス語で話しはじめるような、可愛らしくもちょっとへんな結果につながる。だが、好感を持たずにはいられない。リスペクトせずにはいられない。両脇にびっちりフランス語の単語や表現が書き込まれているのも、すなわち、自分の持てる全てを投じて「一頁の価値を高めたい」からだ。
一頁の価値を高める挑戦は、イコール、ひとつの絵、とくに少女(と、お母様やおばあ様方も)を最大限に可愛くみせようという挑戦だ。
『パリ~東京』は、ファッションもとても素敵だ。もともと中原淳一の手がける雑誌『ひまわり』のイラストをみて絵の道を志した高橋真琴のファションについてのこだわりは、並々ならぬものがある。「古本屋で表紙が欠けたりして安売りしているフランスのファッション誌などを買ってきて研究」(『パリ〜東京』読本)した。
こんなふうに一頁一頁に気合いを入れると、コマとコマのつながりで生まれるストーリーの流れというものはどうしても、ぎこちなくなる。
ストーリーをページで追って見てもらって、楽しかった、おもしろかったとか、そういうんじゃなくて、それを一枚の中に凝縮して、一枚の絵を見るだけでたくさんのページとか絵を味わえるようなことを感じてもらいたいのです。
(荒俣宏の電子まんがナビゲーター 高橋真琴編 eBookJapan)
そしてこのこだわりをいかなる時にも適用すると、量産も、難しい。
というわけで、この作品の発表後まもなく雑誌デビューし、冒頭で述べたような売れっ子マンガ家となるが、やがて週刊誌が主流となる時流に適応できず(というか、せず)、コマ割りのマンガから遠ざかることになる。貸本時代をあわせても、少女マンガを描いていたのはほんの10年足らず。だが、少女マンガに残した功績は、多大だ。
瞳に星
そして瞳に星。
これもやはり、ひとつの絵、一頁の価値をどこまで高くできるか、という挑戦のたどり着いた結果だ。
宝塚もそうですけど、舞台のメーキャップって、すごいですよね。あれは結局、目を目立たすために、すごく大きく描いている。歌舞伎のくまどりもそうでしょ。そういう舞台でできることを絵の世界でできないか、と思って。/そしたら、自然と目が大きくなっていってね。舞台みたいに青いメーキャップなんてできないから。/はじめはちょっちょっと瞳の中に白い点々を描いていたんですが、目が大きいですからだんだん点ではもたなくなってね。いつのまにか星を入れてたんですよ(強調筆者)
『少女ロマンス』
瞳の星は、宝塚や歌舞伎のメーキャップを、マンガの言語で「翻訳」したものだったのだ。目の力を最大限まで高めよう、という試行錯誤の果実だ。
一頁の絵の価値を最大限に高めようとすると、全体としてのストーリーの動きがぎこちなくなる、という副作用があったように、これほど充実した目を描くと、やはり全体への副作用がある。顔が「能面」(←高橋真琴自身が、心情を投影できるからそのほうがいい、と肯定的な意味で使っていることば)のようになる、ということだ。
繰り返すが、私は原則的には、絵のためにストーリーを犠牲にするのは残念だと思う。両立すべきだし、どうしてもどちらか選ばなければならないなら、ストーリーのほうがたいせつだ。けれども稀に、自分の宗旨を棚上げさせるものに出会う。高橋真琴の作品は、そういうものだ。
少女画とグッズ
コマ割りのマンガから離れた高橋真琴は、その後はいっそう「一枚絵」(「少女画」)を充実させる方向にいく。少女マンガ雑誌の表紙、「かぐやひめ」「にんぎょひめ」「おやゆびひめ」などたくさんのお姫様の絵本の挿し絵。ぬり絵、そしてジグゾーパズル、筆箱、筆立て、鉛筆、マグカップ、ハンカチなども手がける。どこから切っても完璧に美しい少女の絵は、グッズとの相性がいい。このグッズ契約のおかげで、絵にこだわることもできたという。自分にあった方法で、自由とやりたいことを守る、運もあるだろうが、ひとつのみごとな生き方だ。
さいきん出版された『あこがれの、少女まんが家に会いにいく。』萩尾望都を含む10人の少女マンガ家が取り上げられているが、付録は、ほかの誰でもなく「高橋真琴オリジナルしおり」だ。ものすごく、かわいい。
----------------------------------------
掲載『マンガHONZ』